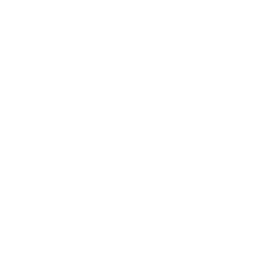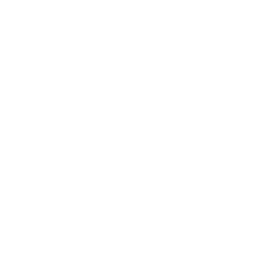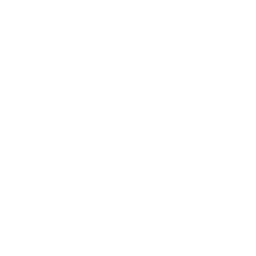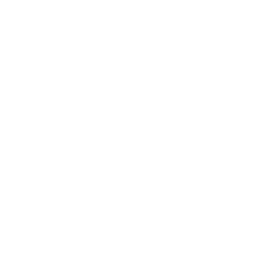セルビアバスケは何が違うのか①「90分の使い方」

セルビア視察レポート第2回です。
現地に着いて2日目から、KKパルチザンの視察が始まりました。
前回書いたように、ここでは文字通り朝から晩まで練習がずっと行われています(食事情のこともいつか書きますが、そんなわけで滞在中の食事もファストフード頼りです)。
いろんなカテゴリが入れ代わり立ち代わり練習できているのは、施設が専有できるからだけではありません。おそらく日本の多くのクラブやチームと違うのが、練習時間です。どのカテゴリも練習は1枠が90分目安で区切られ、それゆえ1日に4〜5カテゴリが活動できています。
実は僕自身も指導しているチームの練習を最大90分にしているので普通の感覚ですが、日本全体からすると短い練習時間なはずです。
では、その90分で何が行われているのか。
一言で説明すると、セルビアの練習ではウォームアップを除いて「バスケットボール」だけをやっているというか、教えています(※個人スキルは、別枠でやっています)。これがいくつかある日本との大きな違いの一つだと感じました。
当たり前ですが、日本でもバスケをやっています。ただ、ここであえてかぎ括弧で「バスケットボール」としたのは、「5人で攻め、5人で守ることをきちんと念頭に置いている」ということを強調したかったからです。もっと分かりやすくいうと、90分の限られた時間を「試合で起きうる状況を想定し、その解決方法を学ぶ」ために使っています。
たとえばドリブルドライブの要素が入ったドリルをやる場合。
オフェンスは必ず複数人(最低2人)が入ります。つまり、オンボールの選手とオフボールの選手がどちらもいる中でドリブルドライブ “から始まるシチュエーション” を練習しています。
日本の育成年代の現場だと、ディフェンスにおいてはカテゴリを問わず1線・2線・3線と全てのポジションの動きを細かく仕込んでいるチームが多いと思います(シェルドリルなど)。セルビアではそれと同じくらい、オフェンスでも各スポットに立ったときの動きを細かくやっているイメージ、といったら伝わるでしょうか。
補足をすると、だからといって選手の動きがガチガチに縛られているとか、そういったことではまったくありません。細かいドリルの話はまた別の機会に紹介できればと思いますが、きちんとした原則、あるいは約束事の中で、選手が自由に動いているドリルがたくさんあります。 そして驚くことに、こうした「ボールマンがこうしたらオフボールの選手はこう」という性質の練習が、10歳から全カテゴリで行われています。

ただ、もちろんカテゴリによって選手のレベルが違うので難易度の差は当然あります。ボールハンドリングや脚力の強さといった視点で見ると、特に13歳、14歳くらいのカテゴリの選手までは「え、こんな感じなの?」と思う日本のコーチも少なくないかもしれません(下手というニュアンス)。
ですが彼らは、「1v1 x 5」ではなく「5v5」をやっています。練習からそれが徹底されていて、ボールハンドリングやクイックネスが日本の小中学生のようではなくても、「うまい」の種類が違うことが、日本との大きな違いの一つです(そして、それが後々大きな差になって現れているのでは、というのがELPISの仮説です)。
この「バスケは5v5をやるもの」という意識は選手にもちゃんと浸透していて、仲良くなった14歳の選手の印象的な言葉などもいつか紹介できればと思います。 それではまた。
ELPISのコンサルティングサービスでは、現在地から目標到達までの道のりや選択肢の整理、進路相談やバスケットボール業界に進むためのアドバイスを行います!留学準備・視察準備から就職・現場活用までを完全サポート!詳細は下記をご覧ください。