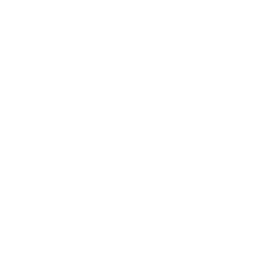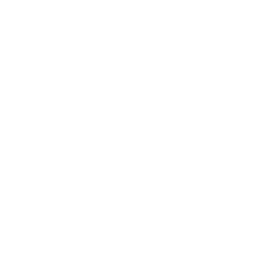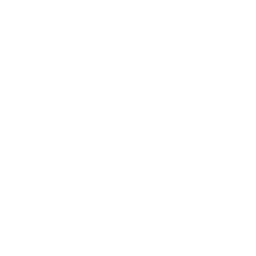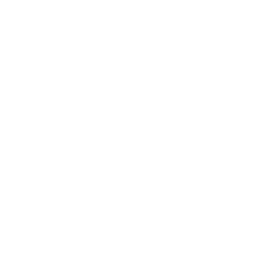逆境を乗り越え、名選手が出続ける理由を探りに。

セルビア視察レポート第5回です。
実は先日、2週間の視察を終えて日本に帰国しました。
現地では合計3つのクラブ、6歳(さらに小さい子も)からプロまで、練習も試合も。この期間で見られる最大限のバスケを見てくることができたはずです。その上で、2週間はとても短かったというか、たとえば「長期的にチーム・選手をどう育成しているのか」だとか、「シーズンの始めの時期は何をしているのか」とか、まだまだ知らないことがたくさんあると感じています。
とはいえ、情報量としては一定以上のインプットになったので、日本でもどんどんそれをシェアしていきたいと思っています。パルチザンについては、当社代表の東頭に縁を繋いでもらったものの、そんなことを知らないコーチや選手からしたら東洋人がいきなり見学に来ただけです。
それなのに、みんな親切にしてくれたり、パルチザン以外の縁ができたり、たった2週間なのにメンターのような人が現れたり、セルビアのバスケ関係者みんなに良くしてもらったという感覚を持っています。だからこそ綺麗事ではなく、その経験を自分だけのものにせず、日本のバスケ界のために少しでも使えたら、と思っています。
そんなこんなで、帰国後もしばらくはこのブログを書き続けていこうと思います。もちろんブログだけでなく、別の形でも情報発信ができたらと構想中です(リクエストをいただけると実現しやすくなります笑)。
さて、前置きが長くなってしまいましたが、今回は「そもそもセルビアという国がなぜバスケ視察に値するのか」ということがテーマです。本来は第1回で書いてもいいような内容ですが、そこは事前にしっかりと構成を練った連載ではなく、あくまで日記的な位置づけでもあるのでご容赦ください笑。
「セルビアって⋯、たしかヨキッチですよね?」
これは、ぼくが指導の現場でセルビア視察に行くことを何人かのコーチ仲間に伝えたときに、実際に返ってきた言葉です。1人でなく、3,4人ほど同じ反応でした。
セルビアはバスケ界でどんな国なのかというと、ニコラ ヨキッチに限らず非常に多くのNBA選手を輩出し続けているところがポイントの1つです。
その元祖といえるのが、初回でも名前を挙げたブラデ ディバッツ。21歳で、パルチザンからNBAドラフトにかかり、ロサンゼルス レイカーズに入団し、長年にわたりNBAで活躍しました。筆者は平成生まれなので、彼がサクラメント キングスで活躍していたのをBS放送でよく見ていました。そしてキングスつながりでいうと、ペジャ ストヤコビッチも同チームの永久欠番になるほどNBAで名を残したセルビア人選手です。僕もシューティングフォームを真似するほど好きな選手でした(セット位置が難しくてやめました)。
彼らがNBAに登場したのは80年代末から90年代なので、ヨキッチ輩出の30年以上も前からセルビア人NBA選手が活躍し続けているのです。それも1人や2人ではありません。最近の有名どころでいえば、ボグダン ボグダノビッチ、ボバン マリヤノビッチなど、常に複数人の選手がNBAで活躍しており、ドラフトにかかった(だけの)選手も足せばもっといます。

選手育成でヨーロッパ内でも有名なクラブ、メガの練習施設に貼られたポスター。このクラブ出身のNBAドラフト指名選手がずらり。
こうした優秀な選手を多数輩出していることもあり、先のパリ2024では銅メダル、2023年のFIBAワールドカップでは2位。最新のFIBAランキングでも2位です(執筆時点)。
ここまでを聞くとたしかにすごいですが、スペイン、フランス、ドイツなど、ヨーロッパにはバスケ強豪国が他にも多くあります。しかしセルビアはそうした国とは一味違うのです。その違いが、一言でいうと国力です。
国力には学問分野によっていくつかの定義があったり、定義の違いはともかく「国の総合的な力」という曖昧さを残した概念だったりするのですが、セルビアは残念ながら上に挙げたスペイン・フランス・ドイツのような国力を持った国ではありません。ダノン、ZARA、BMWと聞けば知らない人はいないと思いますが、セルビアにはそうしたグローバルブランドはありません(※かといって発展途上国でもありません)。
現地に行くとわかりますが、通貨はユーロではなくディナールという独自通貨で、ユーロ圏と比べて物価がかなり安い(ただし、現在の日本と同じか少し高いくらいということをお伝えしておきます)。ある調査によると、セルビアの平均月収は1,269米ドル。日本円換算で19万1619円です(日本の平均月収は約30万円)。これまでのブログではパルチザンの施設の素晴らしさが十分に伝わったと思いますが、実は国単位で見ると、トータルでは日本ほど恵まれた環境ではないのです。
ぼくが視察したクラブの一つが日本でいう町クラブのような位置づけのところだったのですが、そこのU18チームの月謝は35ユーロ(およそ5000〜6000円)。練習回数は週6回です。日本の学生スポーツ界がそもそもボランティアコーチによって成り立ってきてしまった側面(悪い意味で)があるのでなんとも比較しにくい額ですが、同じ首都・東京の町クラブでは月12,000〜15,000円程度、Bリーグの看板がつくクラブだと更に高額になります。ちなみにパルチザンですら、トップの1つ下のU19カテゴリまで、コーチ陣は別の仕事を掛け持ちしながら、世代代表選手らを指導しているのが現実です。

高校生が小学校の体育館で練習する日常。天井の高さは日本と比べてどのくらいでしょうか。サイドラインはどこにあるでしょうか。
このあたりの経済事情からくるバスケ環境については町クラブのレポート回などでふれていきますが、それ以上にヨーロッパの強豪国との差になっているのが、人口です。
セルビアの人口をみなさんご存知でしょうか。
僕も当然最初は知らなかったのですが、なんと約690万人です。フランス約6800万人、スペイン約4700万人、ドイツ約8400万人。ちなみに東京都は約1417万人です。もうこれ以上の説明は不要かもしれませんが、選手発掘においてとてつもなく不利な状況であることは言うまでもありません(部員10人のAクラブと部員100人のBクラブだと、どっちが強い・強くなる可能性がありそうでしょうか?)。
国としての変遷(歴史)などを踏まえるともっといろいろありますが、とにかくこうした事情があるのにもかかわらず、セルビアはFIBAランキング2位で、NBAのシーズンMVPホルダーを輩出することができているのです。そしてその秘けつが、選手育成にあるのではないかとELPISでは考えています。
ちなみに、ヨーロッパ内での比較もさることながら、バスケの本場であるアメリカに行かないのはなぜか?という疑問もあるかもしれません。
コーチの目線で若い年代の選手育成を学ぶ、という意味だと、アメリカには実はコーチのライセンス制度や、国単位での指導ガイドラインのようなものもありません。また、ヨーロッパ各国のクラブや日本とは違い、プロクラブ(NBAなど)がU15やU18といった世代のチームを持って育成しているわけでもないので、一気通貫で選手育成をしているわけでもありません。
こうしたことを踏まえて、「日本が選手育成を学ぶべき場所」としてセルビアに注目しました。
平均身長の差はあれど、セルビアの20倍弱の人口を誇り、トータルで見ると体育館の質や数が圧倒的に優れた日本。あとは僕たちコーチの頑張りというか、選手育成のプログラムさえ整えられれば(もっと言うと盗んでこれれば)、なんとかなりそうな気がしてきませんでしょうか。
強豪校のコーチじゃないから、DCやナショナルチームのコーチじゃないからとか、ミニバスのボランティアコーチだからとか、そういったことではなく、国としての「当たり前」を、あらゆる年代・あらゆるレベルで高めていけたら日本がバスケ強豪国と呼ばれる日も来るかもしれない──。
⋯⋯と、これが今回の視察を思い立った背景です。そして実際にベオグラード市内のいくつかのクラブを見て思ったのは、「言い訳できない」ということです(本当にそうノートにメモした日がありました)。
僕のような代表経験もなければプロ選手輩出実績もない一介のコーチですら、海外視察によって非常に多くのことを感じ取りました。もちろんセルビアだけでなくてもいいのですが、海外視察に行って無駄なコーチ、意味のないコーチは1人もいないと思います。
ということで今回は「なぜセルビアなのか?」という問いについて書いてみたのですが、実際にセルビアのコーチにこの話をぶつけた反応もなかなか興味深かったです。次回以降、またレポートしていきたいと思います。
それではまた。
ELPISのコンサルティングサービスでは、現在地から目標到達までの道のりや選択肢の整理、進路相談やバスケットボール業界に進むためのアドバイスを行います!留学準備・視察準備から就職・現場活用までを完全サポート!詳細は下記をご覧ください。